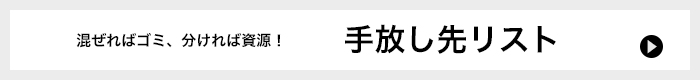おはようございます。
老後を見据え、ひとり暮らしの見直し中のライフオーガナイザーの秋山陽子です。
私はもともと、大きなものを捨てることが苦手でした。
その理由は、「もったいない」というより 「使い切りたい」という気持ちが強かったからです。
そんな私も、片づけを学び、「賞味期限」を持たせることで、「捨てられない」のではなく、「捨てないと決める」ことができるようになリました。
・「〇年後まで使う」と決めて買うもの
・長く使うことを前提に選ぶもの
2つのことを意識することで、無駄な買い物が減り、手放すストレスも少なくなりました。「今だけ」ではなく、「この先もどう使えるか?」を考えることが、ものと長く付き合うコツになっています。

◾️雛人形を「私のもの」として選ぶ(期限なし)
長く使うことを前提に選んだものの一つに、雛人形があります。 23年前、娘の成長を願って迎えた雛人形ですが、選ぶときに大切にしたのは 「私自身がワクワクするかどうか」 と 「飾る&収納スペースに困らないサイズかどうか」 でした。

毎年飾ることを考えると、出し入れに手間がかかると億劫になってしまいます。 そこで、コンパクトで、飾るのが楽しくなるものを選びました。 手のひらに乗る小さめの五段飾りで、飾るたびにワクワクできるものです。
>>>【雛人形収納】箱を変えるだけで、出し入れの手間と時間を半減!!
転勤族だったときは引き出しラックの上に、家を建ててからは畳奥の棚上にと、飾る場所も決めていました。収納も、購入時の箱ではなく、収納しやすいケース を準備しました。そのおかげで、15分あれば出し入れ完了。 おかげで23年間、毎年欠かさず飾ることができています。この雛人形には期限を設けず、これからも毎年、飾る楽しみを持ち続けたい と思っています。
◾️学習机は「将来の私」が使えるものを選ぶ(期限20年)
「子どもの学習机は、子ども部屋で勉強するようになったら買おう」と思っていました。 でも、夫や両親の「買ってあげたい」という気持ちもあり、結果的に購入することに。
そのとき、「台としても使えるシンプルなもの」 という視点で選びましたが、実際に子どもたちが勉強していたのは ほとんどリビング。
学習机を使ったのは、数えるほどしかありませんでした。
「もったいなかったかな」と思っていましたが、今は 私の仕事机 として活躍中!

今年からは、手紙を書く時間も持てるようになり、「子どもの学習机を使っている」ということが、10年経ってまさかの嬉しい気持ちをもたらしてくれました。

椅子を変えたり、引き出しワゴンを別の机と合わせて使ったりして、学習机っぽさを減らして活用 しています。

子どもが使う机としての活用は受験のときくらいでしたが、20年の賞味期限を設定していたことで、その後は私の机として再活用できています。今年は15年目です。あと5年は、もっと活用できないかと、楽しみきろうと思っています。
◾️4年間だけ使う娘のソファ「試しに使ってみる」(期限4年)
娘が大学時代に使っていた一人掛けソファ。

大学生活4年間と賞味期限を決めていたので、手放すことを考え、一度実家に持ち帰りました。ちょうどその頃、犬の介護のためにソファを置かない生活をしていた私。 「新しく買う前に、試しに使ってみよう」と思い、置いてみることにしました。

ただ、色が部屋に合わない…。 そこで、家にあった マルチカバーをかける ことで違和感をなくしました。

すぐに新しいものを買わずに、「試しに使う」「家にあるもので工夫する」。 このおかげで、これからの暮らしでソファが本当に必要かどうか、ゆっくり考えることができています。賞味期限4年と決めたソファ。今は“次”を考える時間をくれています。
「賞味期限を意識すること」は、もの選びの基準の1つになりました。 それは「捨てられないから持ち続ける」のではなく、 「この期間はしっかり使おう」と納得したうえで持つ ということです。「いつか手放さなきゃ」と思いながら持ち続けるのではなく、 「〇年後までは使う」と決めておくと、ものに対するストレスがぐっと減りました。
捨てられないハードルを感じたときの記事はこちら:
・物の要不要で迷うものは、分け方を工夫!「過去」「未来」時系列で分けて集める収納を10年した結果は?
・大きな不用品を実際に処分してわかった、“捨てられないハードル”の乗り越え方
・“もう使わないけれど捨てられない”ゴルフバッグはベッド下へ! 家庭内の平和的解決法、見つけました
あなたは生み出された時間で何をしますか?
何をしたいですか?
心地いい暮らしづくりに役立てれば嬉しいです。
ライフオーガナイザー 秋山陽子
ブログ : うちらしく暮らしやすく