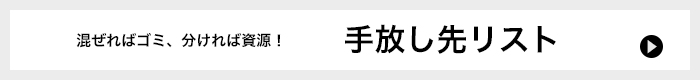おはようございます。
ライフオーガナイザーのさいとう きいです。
この春からお弁当作りがスタートしたみなさん、お疲れ様です……! 栄養のバランスよく、見た目の彩りよく、けれども少しでもラクにお弁当を作るには、どうしたらよいのでしょうか。片づけのプロであり、お弁当作りの先輩でもある8人に、すぐ真似できる時短のコツを聞いてみました。
目次
■ ルールを決めれば、お弁当作りの負担が軽減
● お弁当のおかずは「4色ルール」
ライターのあさおか まみさんは、息子さんが幼稚園児だった頃と高校生だった頃の6年間、お弁当を作っていたそうです。
「お弁当のおかずを考えるとき、4つの色『黄・緑・茶・赤』が揃うようにメニューを組み立てていました。そうすることで、お弁当の彩りが良くなり、私のお弁当づくりのモチベーションになる『美味しそうなお弁当』が楽にできます」

「お弁当の準備は材料の買い物から始まりますが、お弁当に入れる色、詰め方、料理のパターンを決めたことで、買い物のときに迷うことも減りました。また、4色を入れることで、栄養バランスが良くなるのもメリットです」
あさおか まみさんの記事はこちらから:
>>>お弁当のおかずは「4色ルール」にすると、買い物もメニューも悩まない
● お弁当箱選びのマイルールを洗い出す
「夫、高校生長女、中学生次女の3つのお弁当を作っていますが、お弁当3つ分のおかずを用意するのは、正直キツイです……。その分おかず以外のところでラクをしようと考えて選んだのが、『薄型弁当箱 フードマン600』でした」というのは、元ライターの佐藤美香さん。

「お弁当箱選びで絶対にゆずれないマイルールは3つ。①3人とも同じにできるもの、②食洗機対応のもの、③通勤・通学バッグに入るコンパクトなものです。フードマンはこの3つを満たすだけでなく、『汁漏れしづらい』『浅型だから詰めやすい』『パッキン一体型で洗いやすい』というメリットもありましたよ」
佐藤美香さんの記事はこちらから:
>>>3人分のお弁当作り、ラクするために選んだお弁当箱は「フードマン」。その理由とは?
● お弁当に入れる品数を決めておく
フードマンのお弁当箱を愛用している、元ライターの佐藤さんは「毎日、夫と長女・次女のお弁当を3つ作っていますが、次女に食物アレルギーがあるため、魚や玉子など入れることができない食材があります。ざっくりとした種類とスペースを決めたことで、おかずを考えるのがずいぶん楽になりました」

「おかずのスペースのうち、
1/2 主菜:肉系 お肉でご飯が進みそうなおかず
1/4 副菜:黄色系 さつまいもや南瓜などの芋類、コーン、練り物
1/4 副菜:緑系 ブロッコリー、葉物、スナップえんどうや枝豆
その日の気分で多少選択肢があるくらいの緩めのルールが、私にはちょうど良いようです」
佐藤美香さんの記事はこちらから:
>>>もう迷わない!数を決めて、お弁当作りの「めんどくさい」を解消
● 「素材1つ」がルールの時短レシピ
エディターの秋山陽子さんにとって、お弁当作りの負担になっていたのは「メニュー決め」「彩りとバランス」「隙間をうめる副菜選び」だそうです。
「メニュー決めがラクになった理由は、おかずを主菜1つ+副菜2つ+卵焼きに固定したこと。メニューを決めることで、自然と栄養バランスや彩りも整ったので、一気にふたつの課題を解決できました」

「副菜は、晩ごはんで多めに作ったものや、時間があるときにお弁当用に作り置きしたものを冷凍しておきます。決めた数のおかずでお弁当箱が埋まらないときは、家に常備している素材1つを切るだけ、焼くだけ、合えるだけでできる『だけレシピ』が活躍。レシピをスマホに集めておくことで、副菜選びのストレスからも解放されました」
秋山陽子さんの記事はこちらから:
>>>もう悩まない!「ありもの」でつくる時短弁当づくりの3つのコツ
● 「道具」と「食材」の収納ルール
幼稚園から高校までの10年間、娘さんのお弁当を作り続けたライターの浦田友惠さん。「大きくなればなるほど、毎朝のお弁当づくりがしんどくなり、キッチンに立つのが億劫に。そこで、“毎日継続すること”を目標に4つのルールを決めてみたんです」

そのルールとは、
- お弁当の基本の「量と形」を決める
- 冷蔵庫にまとめる「食材」を決める
- 食器棚にまとめる「道具」を決める
- 行事・季節で追加変更するものを決める
「気持ちや手際だけで乗り切ろうとすることをやめ、お弁当に必要な最低限の道具と食材に収納ルールを決めたら、考えることなくルーティンをこなせるようになりました」
浦田友惠さんの記事はこちらから:
>>>お弁当づくり10年!「道具」と「食材」の収納ルールを決めるだけで毎日が楽に
■ スープジャーを使った時短弁当
● 汁物を“1品”としてカウントする
「お弁当のご飯があったかいと嬉しいかな」という理由で、「サーモス」の保温弁当箱を使い始めた服部友美子さんですが、思わぬ時短効果が得られたのだとか。「前日の晩ごはんのおかずに、汁物を多めに用意するようになりました。豚汁、シチュー、おでん、牛丼、ハヤシライスなど、スープジャーに入れたらお弁当のおかずに早変わり」

「朝、何も残っていないときは、粉末のポタージュやわかめスープを溶かして入れることも。そんなときには、別にご飯が進むおかずが1品あれば十分。たとえば、ハンバーグや焼肉のタレで焼いただけのお肉でも、男子は大満足してくれます。ご飯ジャーに炊きたてのご飯をそのまま入れて、すぐフタが閉められるのも嬉しいところ(むしろ、そうしなければ冷めてしまうのです!)。冷ます時間が必要ないのも、時短につながっています」
服部友美子さんの記事はこちらから:
>>>やめられない「高校生男子が喜ぶお弁当」! お弁当箱選びが時短弁当作りの決め手に
● 時短の極み!シリアルをお弁当にする
「夏のお弁当づくり、料理苦手な私の定番は、スープジャーを使った保冷シリアル弁当です」というのは、ライターの下川美歩さん。「スープジャーというと保温調理に便利なイメージですが、保冷もできます。ポイントは、『スープジャーに氷水(分量外)を入れ、フタをして3分ほど予冷すること』と、『保冷後は6時間以内に一度に食べること』」

「私の定番シリアル弁当は、予冷したスープジャーにヨーグルトとフルーツを入れて、シリアルを一緒に持っていくだけ。食べる直前にシリアルをスープジャーに入れてかき混ぜると、ザクザク食感で食べ応えのあるランチになりますよ」
下川美歩さんの記事はこちらから:
>>>夏のお弁当づくりが簡単・時短に! スープジャーに入れるだけ保冷シリアル弁当
■ お弁当作りがラクになる“ひと工夫”
● 玉子焼きも冷凍できるんです
エディターの白石規子さんは、「少しでも段取りよくお弁当の支度ができるよう、食材の冷凍を活用しています。たとえば、お弁当箱にちょっとだけすき間ができてしまったときに便利な温野菜。カットした野菜をスチーマーで加熱したら、お弁当用にラップ。さらにフリージングバッグに入れて、冷凍保存しています」

「夕飯のときにも、ひと工夫。その日に食べる分よりも、多めにおかずをつくって翌日のお弁当分と、さらにいくつかを小分けにして、冷凍庫へ。切り干し大根、五目豆やナムルなど、副菜がいくつか冷凍してあると、本当に便利!
玉子焼きも冷凍できます。お弁当サイズにカットして、一回分ずつ、ラップで包みます。ブロッコリー同様、フリージングバッグに入れて、冷凍保存。朝はラップをはずして、お弁当箱に詰めるだけ。ちょっとした保冷剤代わりにもなりますよ」

白石規子ささんの記事はこちらから:
>>>お弁当の定番おかずは“冷凍保存”。卵焼きも冷凍OK!
● “ちょい足し”でお弁当を華やかに
「料理はあまり得意ではありませんが、お弁当だけは『美味しそう』『また作って』と褒めてもらえます」という水谷のぶこさんが実践しているのは、定番のおかずに“ちょい足し”するだけで美味しそうに見せるテクニック。
「とくに手軽なのは、トッピング。たとえば、肉団子や生姜焼きなど、肉のおかずにゴマをひとふり。ごはんにはゴマの代わりに、ぶぶあられを使うとカラフルで華やかになります。ハンバーグには型抜きチーズもおすすめです」

「卵焼きは溶いた卵に“ちょい足し”するだけで、カラフルに見えて美味しくなります。ほうれん草、明太子、ふりかけ、チーズ、しらすなど、なんでも合います。隙間を埋めるミニトマトは、『しらすと大葉』『ネギとゴマとちくわ』など他の具材と和えると、立派な1品のおかずに。忙しい朝でも簡単にできるので、ストレスなく続けられます」
水谷のぶこさんの記事はこちらから:
>>>簡単にできる! 定番おかずにプラスアルファで、美味しく見えるお弁当づくりのコツ
* * *
年に数回あるか、ないかの行楽弁当なら「気合と根性」で乗り越えられます。けれども、毎日のお弁当作りとなると、「気合と根性」がなくても続けられる小さな工夫(と、手抜き)が必要なんですね。次回は、お弁当作りをラクにする収納の工夫をまとめてご紹介します!
あなたは生み出された時間で何をしますか?
何をしたいですか?
心地いい暮らしづくりに役立てれば嬉しいです。
ライフオーガナイザー さいとう きい
ブログ:SMALL SPACES: 狭くても快適に